
第15回 ヨミウリの化石
小見らトップの選手は、しょっちゅう1対1に付き合ってくれた。だが、ただの練習ではない。必ずコーラを賭けさせられた。高校生の小遣いでは懐が痛むのだが、サッカーがうまくなるためには仕方がないと思った。ミスターヨミウリといわれる伝説の名プレーヤー、ジョージ与那城とフルコートの1対1をしたこともある。これにはさすがに勝てっこねえよと音を上げた。
「貫かれていたのは、日本サッカー協会が定義するサッカーをバカにする姿勢。サッカーってそんなつまんないものじゃないだろう? もっと面白いスポーツだろ? そんな思いがランドには渦巻いていた。そもそもポジションの概念が違ったんだよ。俺らは中盤の3人がポジションをくるくる変えながら攻撃と守備をやる。臨機応変にね。右サイドハーフ、ボランチといった役割はないも同然で、そんな決まり事は意味がないことを知っていた」
当時、クラブチームは異端の存在であり、白井さんたち高校生に公式戦はない。練習試合で高校選手権の常連校を負かし、大学生のチームをチンチンにして「君たち、本当に高校生なの?」と驚嘆された。
とぼとぼ下った坂道
高校3年、受験のために1年のブランクを経て、大学生となった白井さんは再び読売クラブに通った。しかし、3ヵ月で去る決心をする。この先もここでサッカーを続けていく自信を失っていた。そこで、相川亮一(2011年没)の部屋をノックする。相川はデットマール・クラマーに師事し、読売クラブの礎を築いた指導者のひとりである。
相川の返事は至極あっさりしていた。「わかった。じゃあな」。それだけである。白井さんはランドから駅へと続く坂道をとぼとぼ下って帰った。
以降、白井さんは草サッカーの選手としてプレーを続けた。週末、近所のグラウンドに出向き、人数が足りないチームや劣勢のチームを見つけ「どうだい、俺を使ってみねえか?」と声をかける。読売クラブ仕込みの技術だ。さらにスピードとパワーもケタ違いである。周囲とのレベル差は明らかで、バカスカ点を取った。
「特にヘディングには自信があった。ジャンプしたら、バーから頭ひとつ出たからね。バーのてっぺんが見えた。空中で止まり、それからボールをどこに叩き落そうか考える時間があった」
大学卒業後、白井さんは再び読売クラブを訪ねている。もう一度、ここでサッカーをやるために一念発起した。この日のためにコンディションを整え、身体のキレは申し分なかった。事実、紅白戦では個人技で突破し、ゴールも決めた。だが、一方でぬぐえない違和感があった。周囲と呼吸が合わない。パスのタイミングがズレる。やりたい放題の草サッカーに慣れ、いつの間にか顔が上がらなくなっていた。

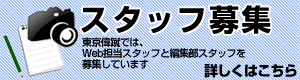








 RSS 2.0
RSS 2.0
