
第7回 ヴェルディとミドリ
仕事が終わって、ぽつねんとしていると誰かが気を遣って話しかけてくれる。それを歓迎する場合とそうではない場合がある。よほど親しい間柄でなければ、会話のやり取りが億劫になるのだ。要するに、同じ場所に誰かいてさえくれれば心の平穏は保たれる。つくづく難儀な性格である。周囲に流されやすい面があり、これだけは早急にどうにかしなければいけないと考えているが、長年連れ添ってきた内面を転換するのは自身に起こす革命に等しい。
東京ヴェルディでの仕事を経て、人見知りはだいぶ改善したように思う。多くのスタッフから何かと話しかけられるおかげだ。誰もが、ミドリ、あるいはミドリちゃんとファーストネームで呼ぶ。幼い頃から、自分の名前を好きだと感じたことがなかった。洋服や小物でも緑色は意識的に避けてきた。「あーなるほど、ミドリだけに」と勝手に納得されるのがいやだった。だが、ここではミドリと気安く呼ばれると、なぜかうれしい。心がパッと明るくなる。中には苗字をすっかり忘れている人がいて、一応ちゃんと憶えてほしいと要求しつつ、そのままでも一向に構わない。もちろん、応援しているクラブは東京ヴェルディだと堂々言える。
スタッフとの付き合いが深まるにつれ、からかわれることが多くなった。冗談が度を過ぎると、表向きは平気な顔をしていても、内心はひどく憤慨している。実はハートは大変繊細で、傷つきやすさはワールドクラスだと自認している。が、生来の性格ゆえ、不満を言えない。せいぜいだんまりを決め込むだけだ。
ヴェルディの役に立つなら
大学卒業後の一時期、ミドリは東京ヴェルディの仕事から離れている。実家がベーカリーを営んでおり、専門学校に通い、パン作りの基本をひと通り覚えた。現在、そちらが本職である。
再び戻ってきたのは、一昨年、マンパワー不足に悩むスタッフが助けを求めたからだった。以来、生業に差し支えない範囲で、試合日に公式記録の配布や授乳室、医務室への案内を手伝っている。報酬はなく、交通費の支給があるだけだ。
試合前、運営本部にいると、ゴール裏のサポーターが掲げる横断幕やゲートフラッグが見える。しばらく立ち止まってそれを見やり、ミドリはいつも泣きそうになるのだ。ヴェルディのサポーターは本当にやさしいな、選手のことを大切に思っているんだな、と。高らかにチャントが響き、思いの束がガラスを隔てた向こうからひしひしと伝わってくる。胸が熱くなり、鼻の奥がツンとする。しかし、仕事中に泣くわけにはいかない。すんっと鼻をすすってごまかす。そこには、その空間にはミドリだけの世界がある。
ときどき、考えるのだ。いつまで私はここにいられるのだろう。現在のヴェルディはお金がない。だから、人件費がかからず、仕事に慣れた自分が必要とされる。いつか、お客さんが大勢入って、スポンサーがじゃんじゃん集まり、クラブ経営が好転したとき、はたして声はかかるのだろうか。
一方で、そんなことはこれからクラブの歩む未来のなかで、フッと一息でけし飛ぶほど小さなものであることはわかっている。自分が特別だとは思っていない。ただ、置いてきぼりにされるような寂しさを想像すると、心にさざ波が立ち、宙ぶらりんな気分になる。
「私ができるところまでお仕事を頑張ろうと思います。ヴェルディの役に立つなら、それだけでうれしい」
どこにでもいそうで、きっとどこを探してもいない。東京ヴェルディのミドリである。
(了)
(著者プロフィール)
海江田哲朗(かいえだ・てつろう)
1972年、福岡県生まれ。獨協大学卒業後、フリーライターとして活動。東京ヴェルディに軸足を置き、日本サッカーの現在を追う。主な寄稿先に『サッカー批評』『週刊サッカーダイジェスト』『週刊サッカーマガジン』『スポーツナビ』など。著書に東京ヴェルディの育成組織を題材にしたノンフィクション『異端者たちのセンターサークル』(白夜書房)。
海江田哲朗 東京サッカーほっつき歩記は<毎月第1水曜日>に更新します

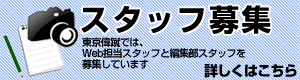








 RSS 2.0
RSS 2.0
