
第7回 ヴェルディとミドリ
サッカーの近くにいたい
ある女性のごくごく個人的な話をしよう。Jリーグの試合会場ではさまざまな人々が働いている。クラブのスタッフ、グッズの販売員、警備員、それに多数のボランティアによって運営が支えられている。ミドリはそのひとり、20代半ばの社会人だ。東京ヴェルディとの付き合いは今年で8年目に入る。
中学生の頃はなんとなくサッカーが好きだった。高校生になり、どうやら自分は心からサッカーを欲しているらしいとわかった。ただし、通っている高校のサッカー部はチャラチャラしていて応援する気になれなかった。がむしゃらに、一生懸命やっている姿が見たいのだ。そこで、たまにJリーグの試合に足を運んだ。
ミドリは大学生になり、初めてのアルバイトを決意する。できればサッカーの近くで仕事がしたいと思った。すると、友人が「求人誌に載っているよ」と教えてくれた人材派遣会社の募集に、Jリーグ運営業務委託とあった。初のアルバイトに不安を覚え、友人に一緒にやってほしいと頼んだ。
アルバイトを始め、期待はすぐに裏切られる。仕事内容はサッカー関係の業務に限定されず、多種多様なイベント会場におけるお手伝いさんであった。役得として試合が見られるかもしれないという甘い考えを抱いていたが、とても実現しそうになかった。気がつけば、一緒にアルバイトを始めた友人はいなくなっていた。
1年目の冬、来年から報道受付の担当を頼みたいとの打診を受け、ようやく居場所らしきものが定まった。通常、報道受付は2人体制で対応し、試合が始まっても遅れてやってくる記者やカメラマンがいるため、休憩時間以外は席を離れられない。ミドリは同僚とおしゃべりをしながら、通路の奥、メインスタンドに通じるドアから漏れ聞こえる音に耳を澄ます。
地鳴りのような歓声が聞こえ、ミドリは隣と顔を見合わせる。
「ゴール、入ったみたい」
「スタジアムDJのアナウンスがあれば、ヴェルディのゴールだけど」
「……聞こえないね」
そんな会話をしながら、どんなサッカーが展開されているのか、ピッチに思いを馳せた。
ゲームが終わり、勝った試合はにこやかに、負けた試合は神妙な面持ちで報道関係者を送り出す。ときには勘違いもあった。てっきり2‐1で勝ったと思ったが、実際は1‐2で負けており、ニコニコ笑顔を振りまいて応対してしまったことをあとで悔やんだ。
誰もがミドリと呼ぶ
アルバイトを始めた当初、ミドリは奇しくもFC東京のファンだった。派遣元は味の素スタジアムで開催されるJリーグの業務を全般的に請け負っており(現在は異なる)、東京ヴェルディとFC東京の両方で仕事を経験している。次第に東京ヴェルディのほうに気持ちが傾いたのは、現場で接するスタッフから感謝と労いの言葉があったからだ。
ミドリは、自分が少々ややこしい性格をしていると自覚している。まず、極度の人見知りである。ちょっと知っている程度の人から話しかけられると、途端に落ち着かない気持ちになる。何を話せばいいのか考えあぐね、窮地に陥ってしまう。そこは人並みのコミュニケーションが取れるまでに、助走の段階で多めに時間が欲しい。かといって、ひとりの時間を好むわけではなく、単独行動は大の苦手ときている。ショッピングは平気だが、飲食店はスターバックスが限界だ。サッカーを見るときは、腕組みしてじっと視線を送る。観戦に付き合ってくれる友人の存在はありがたいが、あれこれ話しかけられ、サッカーの見方を指南されるのはうっとおしく感じる。

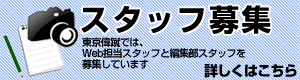








 RSS 2.0
RSS 2.0
