
第13回 サッカー居酒屋(後編)
ちゃんとサッカーを見ようよ
饒舌になるのは、やはりサッカーの話だ。1968年、アーセナルが来日し、日本代表と戦った試合を観戦したこと。ペレ、ヨハン・クライフ、フランツ・ベッケンバウアーに、サッカーというスポーツの楽しさを教わったこと。そして、同い年の釜本邦茂がどれほど傑出したストライカーだったか。
「ここ10数年だったら、小野伸二だね。テクニックがあり、プレッシャーをかけられても平気な顔をしてプレーできる。中田(英寿)や名波(浩)など優れた選手を挙げればキリがないけど、最も印象に濃いのは小野だな。すごい選手が出てきたもんだと思った」
私が話を聞かせてもらった日、藤原さんはシニアリーグに所属するチームで試合をしたあとだった。仕事の邪魔になってはいけないと開店前に時間を取ってもらったが、そんなのは関係なしに近くのテーブルではチームメイトが談笑しながらビールを傾けている。まさに、サッカー仲間の溜まり場であった。
「まさか、70歳を過ぎた自分がプレーしているとは思いもしなかった。昔は大学サッカー部や社会人チームのOBなど、一部の人たちしか自由にサッカーができなかったんだよ。オープンになって、自分たちのようなファンがサッカーを楽しめるようになったのは最近のこと。地域のサッカー協会が環境を整備してくれたおかげだね。それに日本全体が豊かになったんだ。貧しかったらスポーツなんてできやしない。あとは、サッカー観戦に適した球技専用のスタジアムをもっと造ってほしい。今後に望むのは、それくらいかな」
ここ「いなば」を通じて、人間関係が広がった人たちはたくさんいるに違いない。私はその緩やかでいて確かなつながりと、そこかしこに散らばる豊かな実りを想像する。
「でも意味ないよ。やめちゃうもん。お金があったら続けているさ。しょうがないよな」
店舗の賃貸契約は今年11月末まで。藤原さんは膨大な数のサッカーグッズを含めて、丸ごと居抜きで明け渡す準備がある。いくつか話があるようだが、相手はビルのオーナーとの交渉になるため、進展の詳しい様子はわからない。
最後に、私は自分の悩みを藤原さんに相談してみることにした。サッカーは好きで、サッカーについて書く仕事も望んでやっているのだが、時々、ピッチ外の大人の事情にうんざりする。たまに、サッカーそのものを自分から遠ざけたい気持ちになることがある。
「サッカーの世界は政治的な部分だけを切り取れば、汚く見えることもあるよ。俺はこう思ってるね。いいグラウンドでいいサッカーを見せるのが、おまえらの仕事だろ、と。それをわかってるか? わかっていれば、身内で喧嘩しようが権力闘争をしようが、俺には関係ないし、興味がない。好きにやっていいから、ちゃんとスタンバイはしろよ。サッカーを見せてくれよ。そんな感じだね。裏方を見に、スタジアムへ行っているわけじゃないから」
藤原さんは常にピッチを中心に物事を考えるからブレない。持論を聞き、私は胸がすーっとした。
「だいたい、みんな余計なことに構いすぎなの。サポーターの世界もそう。くくられた社会でおおよそ決まった人数になり、そこから決まって腐り始める。どうでもいいことで仲間を批判したり、人間関係の話ばかり熱心になってさ。マンションの自治会みたいだよね。典型的な村社会。バカバカしい話よ。何のためにスタジアムに来ているの? サッカーが見たいんでしょ? 好きなチームを応援したいんでしょ? だったら、ちゃんとサッカーを見ようよ」
そろそろ約束の1時間が経過しようとしていた。私は藤原さんに礼を述べ、席を立つ。店のドアを開けて帰りしなに振り返ると、うれしそうに仲間の輪に入っていく藤原さんがちらっと見えた。
(了)
(著者プロフィール)
海江田哲朗(かいえだ・てつろう)
1972年、福岡県生まれ。獨協大学卒業後、フリーライターとして活動。東京ヴェルディに軸足を置き、日本サッカーの現在を追う。主な寄稿先に『サッカー批評』『週刊サッカーダイジェスト』『週刊サッカーマガジン』『スポーツナビ』など。著書に東京ヴェルディの育成組織を題材にしたノンフィクション『異端者たちのセンターサークル』(白夜書房)。
海江田哲朗 東京サッカーほっつき歩記は<毎月第1水曜日>に更新します

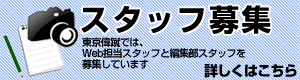








 RSS 2.0
RSS 2.0
